


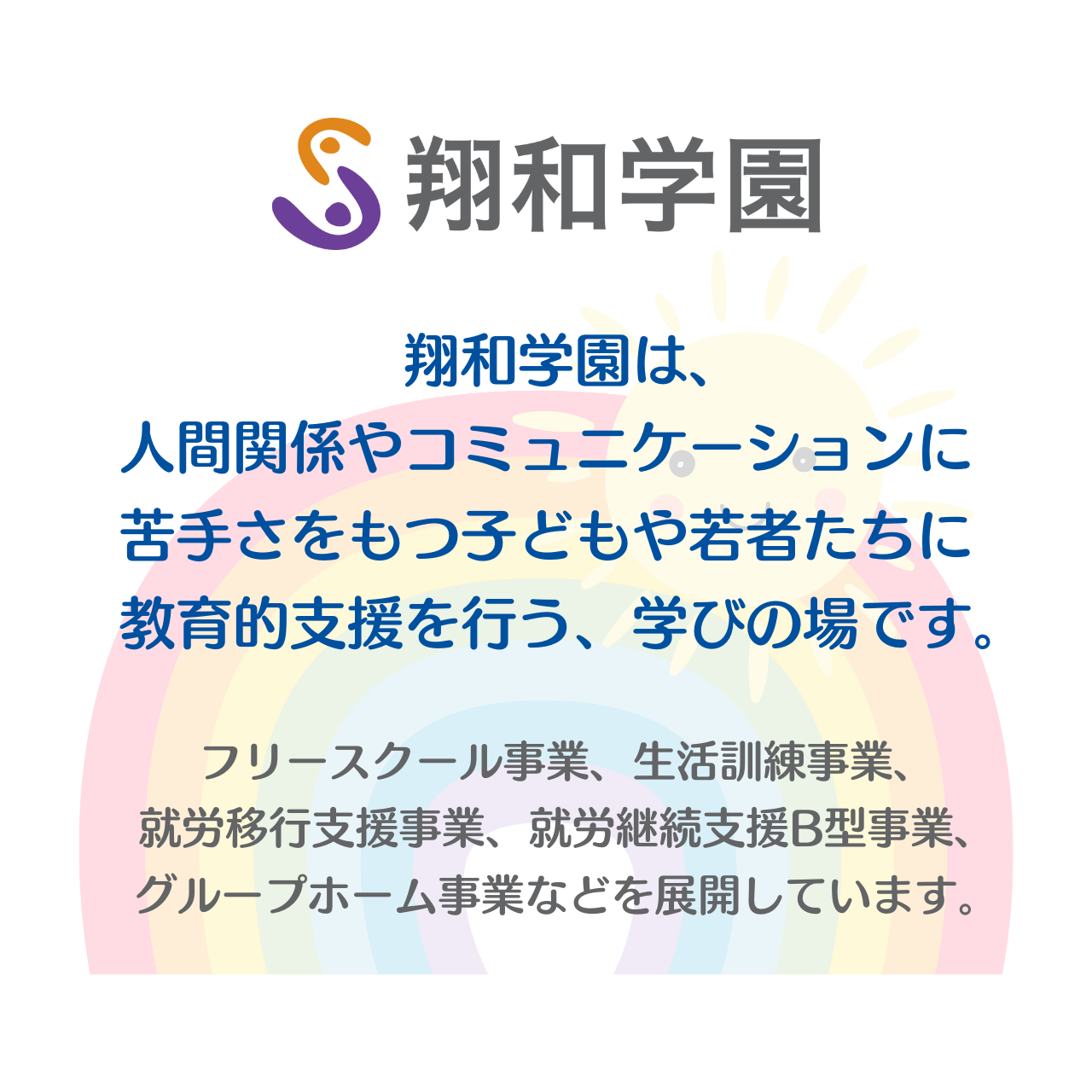
翔和学園は「社会性」を学ぶ学校です。この「社会性」を縦糸に、「生活の質を向上させる」ことを横糸にしてカリキュラムは組み立てられています。そして、実践的な教育システムのもと、段階的な目標達成プログラムを展開しています。教育だけでなく、医療との連携も重視しており、学園専属の臨床心理士の他、どんぐり発達クリニックの宮尾益知医師による月1回の巡回も行われ、より専門的な特別支援教育を実施しています。
学園長挨拶

翔和学園の教育の目的は、「人間の生きていく気力を育てる」ということです。
そのために、翔和学園では、発達障害やそれに類似する苦手さを持つ若者、またそれに起因する不登校・ひきこもり状態にある若者たちに青春を謳歌させることを第一義とします。それが、就労への確かな道であり、安定的・継続的な社会参加に不可欠な要素であると、私たちは考えています。普通の子どもが当たり前に過ごす子ども時代を送らせ、誰もが憧れる青春時代を過ごさせる。そのことを通じて、人間関係を結ぶ力を育み、生きていく気力を育んでいく。そうして、青春時代の思い出を質的にも量的にもたっぷりと心に刻むことこそが、社会に出ていくための確かな道です。
また、私たちは、発達の凸凹をもった子どもたちの能力の谷の部分(凹)を支援するだけではなく、むしろ能力 の峰の部分(凸)を伸ばしていくことを重視した「ギフテッドの教育」を行います。
今までの特別支援教育においては、彼らの苦手さばかり注目されてきました。しかし、彼らは誰もが得意なことを持っていると、私たちは信じています。その可能性を現実にし、他人から認められることによるゆるぎない自尊心を育んでいくことが、「生きていく気力」をより確かなものにします。
「人間の生きていく気力」を育て、安定的・継続的な社会参加を実現すること。それが、我々が目指す教育です。
翔和学園 学園長 伊藤寛晃
翔和学園の理念
人間の生きていく気力を育てる
翔和学園は、小中学部・高等部、大学部、ワークセンター翔和、グループホーム翔和とそれぞれの段階で、「人間の生きていく気力を育てる」ことを通じて社会性を伸ばすことを目的にしています。心理、医療、就労の専門家や保護者との連携により、学習場面や生活場面で困難を抱える子どもの早期発見・療育から就労、そして自立までの一貫した支援の実現を目指します。
- わたしたちの考える「社会性」とは、学力・資格・技能より、よりよい人間関係を作れる力。
- わたしたちの考える「学力」とは、子どもの生活の質を向上させる力。社会性をともなわない教科学習は、しばしば害の方が大きくなる。
- わたしたちの考える「特別支援」とは、「あたりまえのルール」を特別な配慮で学ぶこと。そして、子どもの今と将来をつなげる学力支援。
沿革
翔和学園(旧称ステップアップアカデミー)は、発達障害を抱えていたり、人間関係やコミュニケーションに不安のある学生など、18歳以上の教育的支援を必要とする若者たちが社会性を学び、集団の中で生きていく力を養い、社会的自立をめざすための学校として1999年4月に設立されました。
設立当初、ステップアップアカデミーの前身であるグローバルアカデミーでは、福祉コースとコンピュータコースを柱に、主に就労から自立に向けた技術支援中心のカリキュラムを実践してきました。しかし、活動を続けていく中で、ここに来ている学生達にとって必要なことは、就労や自立をめざすために先ず、日常生活場面での基本的な生活力を身につけることであるということを強く認識するに至りました。
そこで、2002年4月、グローバルアカデミーをステップアップアカデミーと改称、本学園は養護学校や職業訓練校、専門性の高いいわゆる専門学校とは一線を画し、「社会性を学び、集団の中で生きる力を身につける」という目的を第一に掲げ、実践する学園として生まれ変わりました。
2004年4月に対象を拡大して高等部を設立、さらに2005年10月には小中学部を開設し、小中学部から高等部、大学部、そして社会的自立へと一貫した特別支援教育をめざし活動中です。
そして、ステップアップアカデミーは2006年4月より呼称を改め、小中学部、高等部、大学部を総称して「翔和学園」とし、さらなる飛躍を遂げます。
特別支援教育
一貫した特別支援教育
翔和学園では、小中学部・高等部、大学部、ワークセンター翔和、グループホーム翔和とそれぞれの段階で、「人間の生きていく気力を育てる」ことを通じて社会性を伸ばすことを目的にしています。心理、医療、就労の専門家や保護者との連携により、学習場面や生活場面で困難を抱える子どもの早期発見・療育から就労、そして自立までの一貫した支援の実現を目指します。
翔和学園の理念
人間の生きていく気力を育てる
- わたしたちの考える「社会性」とは、学力・資格・技能より、よりよい人間関係を作れる力。
- わたしたちの考える「学力」とは、子どもの生活の質を向上させる力。社会性をともなわない教科学習は、しばしば害の方が大きくなる。
- わたしたちの考える「特別支援」とは、「あたりまえのルール」を特別な配慮で学ぶこと。そして、子どもの今と将来をつなげる学力支援。
翔和学園がめざす教育
学年ではなくその子の今にあわせた学習
翔和学園では、生徒理解に置いて専門家のアドバイス、各種検査、成育歴をはじめとする保護者からの情報を基に、教師の観察に基づく所見を重ね合わせることを積極的に行います。学生が学んで身につけたことを実生活で活かせるようにするところまで保障しようというのが翔和学園のめざす教育であり、「生活の質を向上させる」ことが大切であると考えています。
- 学生一人ひとりの個性や特性を、客観的に理解する。
- 客観的な理解に基づいて、指導を研究する。
- 研究した指導を、実践する。
顧問紹介
宮尾益知 医師
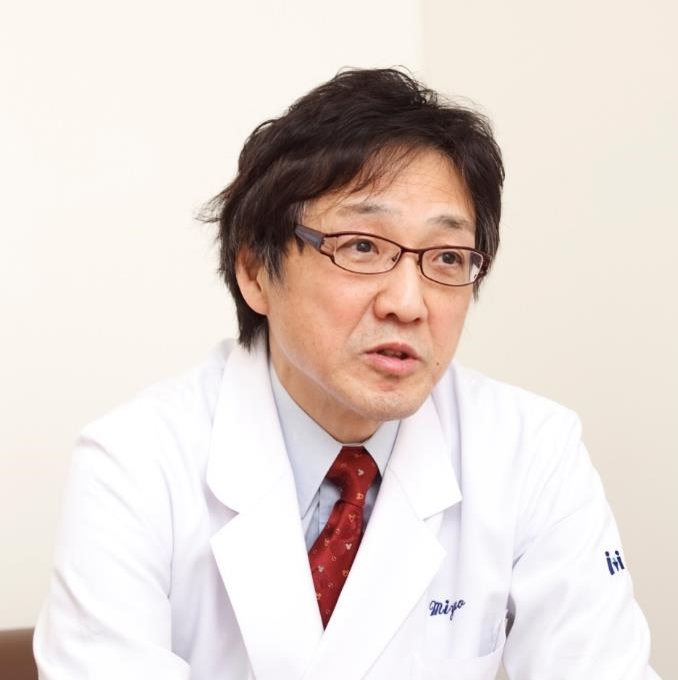
元 国立成育医療センター こころの診療部 発達心理科医長
どんぐり発達クリニック 名誉院長
ギフテッド研究所 理事長
主要著書
『発達障害をもっと知る本―「生きにくさ」から「その人らしさ」に 』
『アスペルガー症候群 治療の現場から』
『アスペルガー症候群 子どもの特性を活かす!』
『自分をコントロールできないこどもたち―注意欠陥/多動性障害(ADHD)とは何か? 』
『ADHD・LD・高機能PDDのみかたと対応―「気になる子ども」へのアプローチ』 ほか多数
発達障害の子どもへの支援において、医療との連携は欠かせません。宮尾益知先生には、2か月に1回の学園訪問による教育指導及び、教員研究会・ケース会議に参加していただき、アドバイスをいただいています。診察室ではわからない、学校・授業の現場を見ていただくことで、特別支援に活かしています。また、他の医療機関・ドクターとも連携するため、生徒、保護者、主治医の方々の同意の上で、診察の同席をさせていただいています。
川端秀仁 医師

かわばた眼科 院長
浦安市学校保健会 会長
ギフテッド研究所 副理事長
翔和学園では毎年、眼科検診を行っています。かわばた眼科では、視力だけではなく、「視覚機能を通して見る」という視点で、「視機能」「視知覚」「認知」の検査をしています。発達の問題が「視覚」にある場合も多く、授業の中では、川端先生開発のトレーニングを取り入れて実施しています。
パンフレット
デジタルパンフレットは、パンフレットページより閲覧いただけます。
紙パンフレットをご希望の方は、お問い合わせフォームより資料請求ください。
翔和学園ってどんなところ?
卒業生・保護者様の声
卒業生の保護者より
正直周りを見ると同じ年の同じような子はもう就職していたり専門学校へ行っていたりで、我が子はこんなのんびりで良いのかと焦る気持ちもありました。でも、今の歳で味わって欲しかった。今しかできない「青春」を身体中で感じ表現している姿を見て本当に良かったと思いました。
卒業生のスピーチより
過去のいじめが原因で声を聞かれるのが嫌になり、全くしゃべらなかった高校生活を過ごしました。今僕の中には沢山の光りがあります。それは、思い切り笑える自分、面白い自分、明るい自分。まだまだ沢山の光りがあるけれど、それをくれた友達が大好きです。
作文「10年前の僕へ」より
もう泣かないでいいよ。もう、そんなに狭い所で人の目を気にしなくても大丈夫だよ。この先、素敵な仲間たちと出会うから、でも何があるのかは、まだ君には教えてあげないね。この先で様々なことにぶつかり、きっとこの学校にたどりつき、幸せになっているから・・・。
翔和学園 Before After
大学受験失敗から劇的に変わり、大学進学(卒業生Aさん)
大学受験に失敗し、浪人生活のなかで生活リズムの乱れとともに勉強も成果が出ないまま、3年間ひきこもり状態が続きました。「抑うつ状態」を主訴として精神科を受診後、発達障害傾向との医師の判断のもと、翔和学園に入学しました。入学当初は週1回の登校からはじめ、徐々に日数・時間を増やすことで、1年間で生活リズムを取り戻すことができました。2年目は学園のプログラムを行いながら、大学進学という希望ができ、受験勉強にも取り組みました。私の特性と将来のキャリアイメージのマッチングを大学進学を全力でサポートしてもらい、無事に大学に合格できました。
対人関係のトラブルを克服(保護者Bさん)
小中学校では人間関係が苦手だったため、通信制高校に進学。課題提出などは全く問題なく、4年で卒業しました。「対人関係が苦手のままでは心配」という保護者のニーズにより、翔和学園に来談。入学当初は「人と関わらずに生きていく」と言っていましたが、文化祭や合宿を通じて人と上手く関われる成功体験を積んだことで、「本当は友達が欲しかった」と語るようになっていきました。保護者としては親亡き後の生活を見越して親離れもさせたいという思いがあり、当学園のシェアハウスに居を移して通学を開始。対人関係だけではなく、自活に向けても頑張っています。
専門学校中退、得意を活かして専門学校に再度進学(卒業生Cさん)
専門学校進学後、対人関係のトラブルで精神的な不調を来たし、中退。精神科で発達障害の傾向を指摘され、当学園に来談。入学後は、対人関係に対する恐怖感が強かったため、入学当初は個室での1対1の個別対応からスタートしました。自分が得意とするIT分野の知識を通じて少しずつ同級生と関われるようになり、文化祭では仲間との共同プロジェクトも達成。対人関係の苦手さを克服し、卒業後はプログラミングの専門学校に進学しました。
高卒認定資格を取得し、進学を果たす(卒業生Dさん)
小学校3年生から不登校になり、小中学校は数日登校したのみで終了。その後3年間ひきこもってしまい、翔和学園に来談しました。入学当初は多動・多弁・注意欠陥により学習困難な状態が続きましたが、小学校2年次 にコンサータを服用し、中断している経過があったことから、主治医を訪問。コンサータの服用を再開したことで、行動が安定しました。医療と密接な連携をとることにより、2年間で高卒認定試験に合格し、専門学校へ進学しました。
